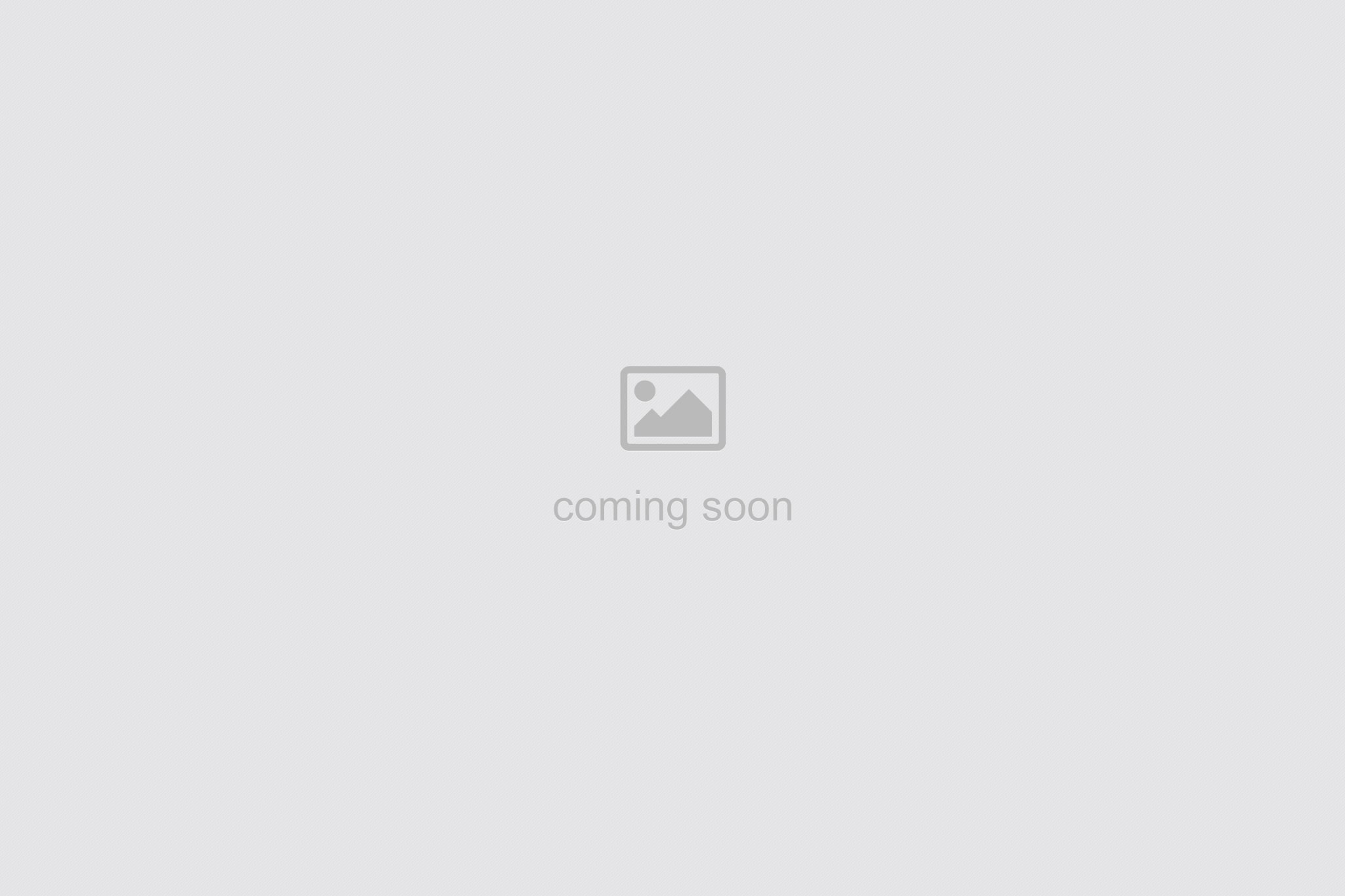目次
社会福祉協議会は、住民が主体の民間団体(法人)です
高齢者になっても、心身に障がいがあっても家族や友人と共に、住み慣れた地域で、いつまでも幸せに暮していきたい。そんな願いを実現していくため、住民相互で力を合わせ、地域の福祉問題に取り組み、解決していくこと。そして誰もが安心して暮すことのできる、思いやりのある福祉のまちづくりに向けて積極的に取り組んでいく住民主体の団体。それが「社会福祉協議会」です。
定款 (294KB) |
現況報告書
現況報告書(令和5年4月1日) 現在 (1842KB) |
組織図
組織図 (214KB) |
野洲市社会福祉協議会 理事・監事・評議員名簿 (130KB) |
野洲市社会福祉協議会 役員の報酬等に関する規程 (93KB) |
野洲市社会福祉協議会 評議員の報酬等に関する規程 (105KB) |
令和6年度 事業計画・予算
【基本理念】「すべての人が ともに生き ともに支えあう安心して暮らせるまち やす」
【基本方針】「おたがいさま」と「少しのおせっかい」
【基本方針】「おたがいさま」と「少しのおせっかい」
少子高齢化・核家族化の進行、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯などが増加し続ける中、家庭内や地域での人間関係が希薄化し、地域での課題解決が難しくなっています。また、厳しい経済状況により生活困窮、ひきこもりや権利擁護の問題など、地域における生活課題は複雑かつ多様化しています。加えて、新型コロナウイルス感染症が昨年5月に感染症法上の5類に移行されましたが、3年に及ぶコロナ禍を通じて、様々な地域生活課題が顕在化しており、孤独・孤立の問題が深刻化するなか、感染防止対策のために制約を受けてきた地域福祉活動やボランティア活動の再開を支援するとともに、多様な人々の参画を得て、新たな活動を広げていくことが求められています。
このような状況の中、本会では、国がすすめる地域共生社会の実現に向けて、野洲市と一体的に策定した「第3期地域福祉基本計画」の基本理念である『すべての人が ともに生き ともに支えあう 安心して暮せるまち やす』の実現に向けて、「おたがいさま」と「少しのおせっかい」の2つのキーワードを基本方針として、地域の多様なニーズや福祉課題に応えるため、地域住民やボランティア、福祉関係団体、市と連携協力しながら各事業に取り組んでまいります。
また、全国各地で台風や集中豪雨、地震等の災害が起こっており、いつ起きても不思議ではない自然災害に対する備えが求められています。昨年度、関係団体等と協議をすすめてきた地域での見守り・支え合い活動や気にかけあう関係づくりを進めるための組織づくりの推進並びに野洲市防災サポート連絡会において、平時から関係者同士がお互いの強みを共有し、さまざまな視点で防災・減災への対応策を協議するネットワークのさらなる深化にむけて取り組んでまいります。
さらに、これらの活動を進めるため、令和5年度に本会としての経営ビジョンや目指すべき方向性を定めた第2次中期経営計画(令和6年度~令和10年度)の1年目として、安定した法人運営を実践するとともに、組織体制の強化や職員の専門性の向上、経営基盤の確立に努めてまいります。
令和6年度 事業計画 (442KB) |
令和6年度 事業予算 (494KB) |
令和5年度 事業報告・決算
【基本理念】「すべての人が ともに生き ともに支えあう 安心して暮らせるまち やす」
【基本方針】「おたがいさま」と「少しのおせっかい」
【報 告】
令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が感染法上の5類に移行されましたが、様々な地域生活課題が顕在化しており、生活に大きな影響を及ぼし続けています。地域では人と人とのつながりが希薄になり、生活領域における支え合いの基盤が脆弱化し、孤独・孤立の深刻化、より複雑化・複合化した課題を抱え、対応が困難なケースが浮き彫りとなるなど、様々な生活・福祉課題が表面化しています。また、物価高騰も重なり、生活困窮者の増加を引き起こしています。
国では社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、自治会やボランティア団体をはじめ、多くの地域住民が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現に向けた取り組みが進められています。
このようななか本会では、地域のつながりの重要性が益々高くなってきており、今まで進めてきた地域福祉活動や福祉団体、福祉施設、ボランティアとのつながりを活かしながら、複雑化する地域ニーズに対して、第3期野洲市地域福祉基本計画の基本理念である『すべての人が ともに生き ともに支えあう 安心して暮せるまち やす』の実現に向けて「おたがいさま」と「少しのおせっかい」の2つのキーワードを基本方針として各種事業を進めました。
特に今年度は、市内で自然災害による被害が発生したときに求められる対応について、平時から関係団体同士がお互いの強みを共有し、連携して効率的な活動ができるように野洲市防災サポート連絡会の立ち上げや、地域での見守り・支え合いを通した福祉のまちづくりを目指して、地域の実情に応じた、それぞれの地域ならではの仕組みづくりに向けた取組みに努めました。
また、本会の目指すべき姿を明確に示した「第1次中長期経営計画」が、本年度をもって計画期間が終了するため、組織全体で課題を共有し、地域住民とともに福祉のまちづくりを進めるため、本会の果たすべき使命や理念を明確にし、その実現に向けた 事業 展開 、組織、財務に関する 今後5年間の具体的な取組を示すため、野洲市社会福祉協議会第2次中期経営計画を策定しました。
令和5年度 事業報告 (3895KB) |
令和5年度 決算報告 (1510KB) |
令和5年度 事業計画・予算
【基本理念】「すべての人が ともに生き ともに支えあう 安心して暮らせるまち やす」
【基本方針】「おたがいさま」と「少しのおせっかい」
今日の社会福祉を取り巻く環境は、高齢化の急速な進展や人口減少、家族機能の弱体化といった社会構造の変化、さらには新型コロナウイルスの影響による生活困窮、孤立や孤独などの複合的な課題を抱える人の増加など、様々な生活・福祉課題が表面化しています。また、ウクライナ情勢等の国際秩序の不安定化、資源価格や消費物価の高騰などにより日常生活にも大きな影響を受けています。
さらに、近年全国的に発生している大規模な自然災害は、突如として人々の日常生活を脅かす恐れがあり、住み慣れた地域で安心して生活していくためには、地域住民をはじめ、社会福祉協議会、行政、民生委員・児童委員、社会福祉関係者等が、日頃から連携し、それぞれの地域において「おたがいさま」と「少しのおせっかい」の基本方針のもと、見守り活動による助け合いや支え合いの関係性を築き、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し災害に強いまちづくりを進める必要があります。
これらの課題に対応すべく国においても地域の特性や生活・福祉課題に応じた住民参加による「地域共生社会」の実現に向けた取組みなど、新たな施策や仕組みづくりが進められています。
このような状況のなか、本会では、令和2年3月に策定した「第3期地域福祉基本計画」の3年目となる今年度において、地域住民自身が自分たちの住む地域の課題を発見・共有する中で、住民自らが 主体的に参画し、地域課題を解決する「互助」の取組みを拡充するため地域住民、関係機関や団体と連携、協働して進めていきます。
令和5年度 事業計画 (419KB) |
令和5年度 事業予算 (488KB) |
令和4年度 事業報告・決算
【基本理念】「すべての人が ともに生き ともに支えあう 安心して暮らせるまち やす」
【基本方針】「おたがいさま」と「少しのおせっかい」
【報告】
地域社会を取り巻く環境は、少子・高齢化、人口減少の進行、家族機能の変化、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、地域や家庭、職場など、住民の生活領域における支えあいや助けあいの基盤が弱まっており、住民や地域が抱える課題は、複雑・多様化しています。
さらにはウクライナ情勢等の国際秩序の不安定化、資源価格や消費物価の高騰などにより日常生活にも大きな影響を受けており、生活困窮、孤立や孤独などの複合的な課題を抱える人の増加など、様々な生活・福祉課題が表面化しています。
このような状況の中、本会では、国がすすめる地域共生社会の実現に向けて、野洲市と一体的に策定した「第3期地域福祉基本計画」の基本理念である『すべての人が ともに生き ともに支えあう 安心して暮せるまち やす』の実現に向けて、「おたがいさま」と「少しのおせっかい」の2つのキーワードを基本方針として、地域の多様なニーズや福祉課題に応えるため、地域住民やボランティア・福祉関係団体、市と連携協力しながら各事業に取り組んできました。
特に、地域の居場所づくりへの支援では、市内3箇所で不登校やひきこもり、高齢者の閉じこもり予防など、人が集うことで当事者や家族がその人らしい生活の送り方を見つけるきっかけづくりができる活動の中で、互いの困っていることや悩みを安心して話せる場が生まれ、住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう地域住民が支えあい、一人ひとりの暮らしと生きがいを地域とともに創っていくことを実現する取組みができました。
また、本会の安定した健全経営を目指し策定した「第1次中長期経営計画」は、今年度が4年目となり、事業効果、効率性、地域ニーズを重視した経営への転換と組織基盤の強化など、計画に基づいた取組を推進しました。
令和4年度 事業報告 (4295KB) |
令和4年度 決算報告 (2113KB) |
事業所一覧
事業所名 | 住所 | TEL・FAX |
総務課 | TEL:077-589-4683 FAX:077-589-5783 | |
地域福祉課 | ||
相談支援課 | ||
在宅支援課
| TEL:077-589-5741 TEL:077-589-6664 FAX:077-589-5783 | |
学童保育課 | TEL:077-589-4683 FAX:077-589-5783 | |
野洲第1学童保育所 | 〒520‐2331 野洲市小篠原2142番地17 | TEL:077-586-2253 FAX:077-587-0107 |
野洲第2学童保育所 | TEL:077-586-1617 FAX:077-587-0107 | |
野洲第3学童保育所 | TEL:077-587-5913 FAX:077-587-0107 | |
野洲第4学童保育所 | TEL:077-587-5914 FAX:077-587-0107 | |
野洲第5学童保育所 | TEL:077-587-5915 FAX:077-587-0107 | |
野洲第6学童保育所 | TEL:077-587-5916 FAX:077-587-0107 | |
野洲第7学童保育所 | 〒520-2331 野洲市小篠原1156番地4 | TEL:077-586-6547 FAX:077-586-6548 |
北野第1学童保育所 | 〒520‐2362 野洲市市三宅248番地 | TEL:077-588-4402 FAX:077-588-4402 |
北野第2学童保育所 | TEL:077-588-4402 FAX:077-588-4402 | |
北野第3学童保育所 | 〒520-2362 野洲市市三宅252番地1 | TEL:077-587-3583 FAX:077-587-0205 |
北野第4学童保育所 | TEL:077-587-3584 FAX:077-587-0205 | |
北野学童保育所(音楽室) | 〒520‐2362 野洲市市三宅240番地 | TEL:090-1958-7286 |
三上第1学童保育所 | 〒520‐2323 野洲市三上111番地 | TEL:077-587-4904 FAX:077-587-4904 |
三上第2学童保育所 | ||
祇王第1学童保育所 | 〒520‐2316 野洲市上屋1295番地 | TEL:077-587-0353 FAX:077-587-0353 |
祇王第2学童保育所 | ||
祇王第3学童保育所 | 〒520‐2316 野洲市上屋1295番地(小学校グランド内) | TEL:077-586-3411 FAX:077-587-0104 |
祇王第4学童保育所 | TEL:077-587-6464 FAX:077-587-0104 | |
祇王第5学童保育所 | TEL:077-587-6465 FAX:077-587-0104 | |
祇王第6学童保育所 | TEL:077-587-6466 FAX:077-587-0104 | |
篠原第1学童保育所 | 〒520‐2313 野洲市大篠原1414番地 | TEL:077-588-1266 FAX:077-588-1266 |
篠原第2学童保育所 | ||
中主第1学童保育所 | 〒520‐2423 野洲市西河原712番地 | TEL:077-589-6306 FAX:077-589-6306 |
中主第2学童保育所 | TEL:077-589-6306 FAX:077-589-6306 | |
中主第3学童保育所 | TEL:077-589-6673 FAX:077-589-4355 | |
中主第4学童保育所 | TEL:077-589-6674 FAX:077-589-4355 |
福祉サービス苦情解決制度
苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員 (91KB) |
次世代育成支援対策推進法に関する取組み
一般事業主行動計画 (52KB) |
女性活躍推進法に関する取組み
一般事業主行動計画 (44KB) |
一般事業主行動計画策定にかかる現状分析 (107KB) |